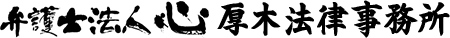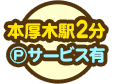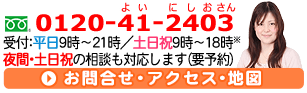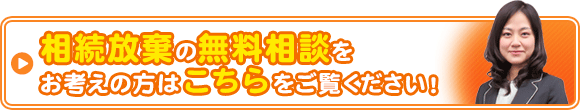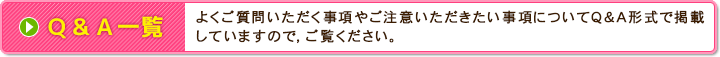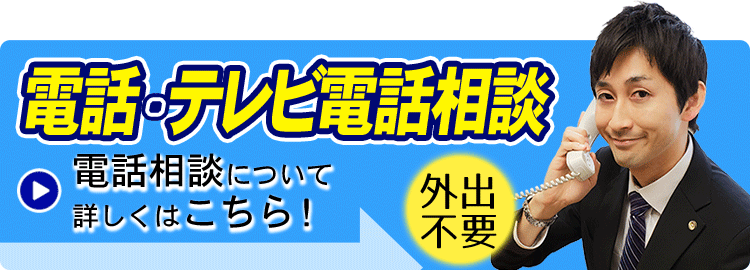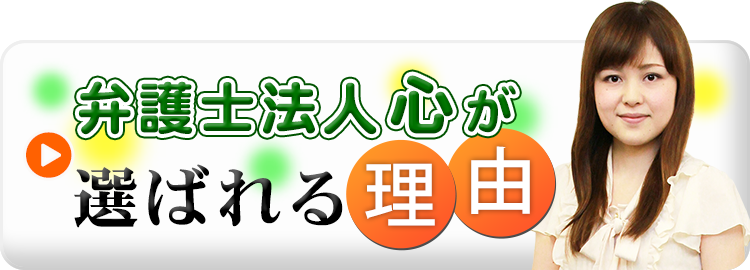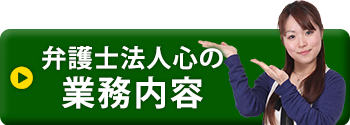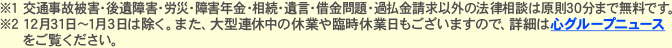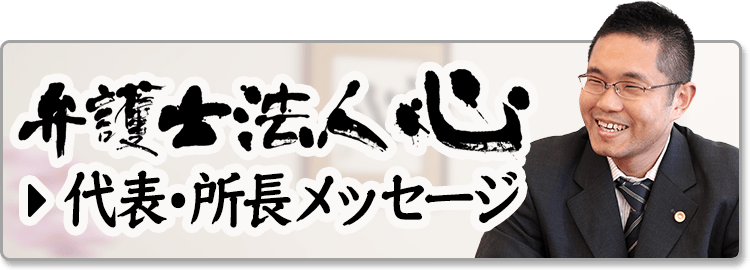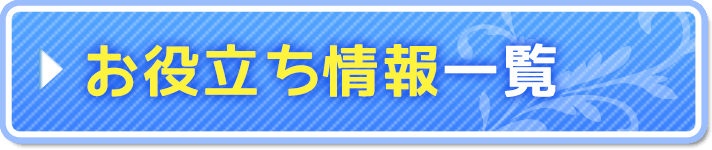相続放棄の熟慮期間とは何か
1 なぜ熟慮期間を設ける必要があるのか
相続放棄の熟慮期間とは、相続を承認するか、放棄するかを判断するために熟慮してよいとされる期間を指します。
起算日から3か月と言われています。
相続放棄は、相続権を放棄するという重要な行為です。
例えば「親父が亡くなったけれど、親父が生前話していた通り、たくさん財産があるのかもしれない。でも親戚のおじさんがこの前の正月にコソコソ叔母さんと話していた通り、借金がたくさんあるのかもしれない。親父が亡くなった後、親戚のおじさんにそれとなく聞いてもとぼけられてしまい、どうしてよいかわからない」というときに、そもそも被相続人である父親の財産を調査する期間、そして相続財産(負債含めて)が出そろったところで、親父の採算を相続するのかどうかを決断する、そのための期間が熟慮期間です(調査、判断の期間を与えて、相続人の適切な意思決定を促すための期間)。
また放棄してしまうと、法律上、その放棄の撤回は許されていない(民法第919条第1項)ので、慎重に判断する必要があります。
2 なぜ3か月なのか?6か月でも良くないですか?
財産調査、特に第三者の財産を調査する場合、相当な時間や手間がかかることが想定されます。
なぜなら第三者の財産を調べるには通常、当該第三者の許可、または許可なくとも第三者の財産を調査できるだけの正当な理由が必要だからです。
とすれば、被相続人の相続財産を調査する期間が、たったの3か月というのはちょっと短すぎやしないか、という意見もあります。
しかし、通常被相続人と相続人とは血縁関係にあり、相続人は生前から被相続人と同居している等の理由で、被相続人の財産状況を事実上知りうる立場(配偶者、子、親)にあることが多いです。
法律上の相続人であれば、通常の第三者に対する財産調査と比べて、被相続人の財産を預かる金融機関等から情報開示がなされる可能性はかなり高いということになります。
また、いつまでも調査だ、調査だと言って、相続するかどうかを相続人が定めなければ、被相続人の債権者などは身動きが取れなくなってしまうので、熟慮期間は長期にすべきではないという考え方もあります(相続人の意思決定遅延による法律関係の不安定)。
そこで、そのような特殊事情を考慮して、財産調査期間であり、相続検討期間でもある熟慮期間を、6か月ではなく、比較的短い3か月に定めたものと考えられます。
3 熟慮期間の起算点はいつか
熟慮期間が3か月と短い期間であったとしても、その期間の開始の起算点を遅らせてしまえば、事実上その熟慮期間は長くなるということもありえます。
しかし、相続放棄の熟慮期間が認められた趣旨(調査、判断の期間を与えて、相続人の適切な意思決定を促す、及び相続人の意思決定遅延による法律関係の不安定を防ぐなど)から考えると、当該相続人に対して、不当に長期間の熟慮期間を付与する結果になることは不適切であります。
具体的には「被相続人が亡くなったこと」、そして「自身が相続人であること」を知った時を「自己のために相続の開始があったことを知った時」として、3か月の起算点とすると言われています。
そこまでわかれば普通は、被相続人の相続財産についてどうするべきかを考えるだろうという理由です。
それでは、特殊事情がある場合はどうでしょうか。
ア 「あいつ(父)には財産がない、借金まみれだ」と、父の生前から叔父さんに言われていたので、特に調査せずに、同居していた父の死後3カ月以内に相続放棄した。ところが父の死から2年後に父の財産(1億円)が発見された。
→「まさかのプラス財産が発見されたので、その発見時から3か月を熟慮期間にしてほしい。」
イ 彼は南米を旅していて、父の死に目に会えなかった。父の死後2年して帰国し、その時初めて父の死を知った。そして父の借金が1億あったと知った。
→「本当に父の死を知ったのが帰国してからだったので、問答無用で1億円の債務を相続させられるのはおかしい。せめて父が亡くなったことを知ってから3か月にしてほしい。」
ウ 特に調査もせず、「よ~し相続するぞ~」と心に決め、父の没後から父の遺産(現金)で豪遊したものの、父の死から2年後、金融機関の通知などから多額の債務(1億円)が発覚した。
→「確かに相続財産に手は付けたけど、その後1億円の債務が出て来たのは想定外なので、その債務の存在を知った時から3か月を熟慮期間にしてほしい。」
それぞれのケースについて、実務上の対応を見てみましょう。
アのケースでについて
すでに相続放棄してしまっているので、原則としてその撤回はできません。
したがって、あとで相続財産が発見されても、放棄をした相続人は相続財産分配に与ることはできません。
それでは今回の場合、彼はどうすればよかったのでしょうか。
3か月間調べても、財産や負債の内容が確定しないなと思った場合、裁判所に対して、熟慮期間の伸長許可を求める方法もあります。
「今回の件、金融機関に対する調査は簡単ではないので、時間が必要です!」と裁判所に申立をして、必要な期間の許可を得ます。
「彼は叔父さんの言葉に惑わされずに相続財産調査を続け、時間が足りない場合は裁判所に期間の伸長申立をして、財産負債の調査を継続した。そのうえで、放棄するか、承認するかを決めた。」というのが正解に近かったのかもしれません。
イのケースについて
長期間の南米旅行などで連絡不通の状態が続く場合、肉親の消息を知ることが難しい状況は、情報伝達方法が発達した現代社会でも起こりえます。
そのような場合、お父さん亡くなってから3か月経過したから、もう相続放棄できないよというのはあまりにも酷であります。
したがって、そのような場合、被相続人の死亡時ではなく、「被相続人の死亡の事実を知ったこと」が起算点になると言われています。
なお、熟慮期間を延ばすためだけに、父親と同居していたのに「いや~、親父が死んだの、全然知らなかったよ!」ととぼけることが許されるわけがありません。
前出の長期南米旅行による不在や、父とは小さい頃に生き別れになり、消息は勿論、存在すらおぼろげであった等、被相続人の死亡の事実を知らなかった事情を具体的に明らかにすることが必要です。
ウのケースについて
一見、債務の存在を知らなかったので、その知った時から熟慮するという話もなくはないのでないかと思われます。
しかしウのケースにおいて重要なのは、「相続放棄の判断をする前に、お金を使ってしまったこと、もっと言えば親の金で豪遊したこと(自分のお金として亡き父の金を使ったこと)」であります。
このようなことを法律上「法定単純承認」と呼称し(民法第921条各号)、このような法定単純承認事由があった場合、相続を単純承認したものとし、放棄は許されないとルール化されています。
したがって、調査、熟慮する前提として重要なのは、「相続する(承認)か、しない(放棄)かを決める前に、被相続人の遺産をいたずらに使ってはいけない」ということです。
この場合、彼は「親父の財産を使う前に、一旦相続財産は凍結して、相続するかどうかは家族みんなと相談して慎重に決めよう。」と、慎重に財産(負債)調査を進めるべきでした。
4 相続放棄の判断は慎重に
以上の通り、相続放棄の熟慮期間について説明をしてきましたが、理解を進めるにあたり、民法第915条第1項本文「自己のために相続が開始したことを知った時」の解釈を理解することはもちろん、「法定単純承認」の内容(民法921条)、熟慮期間伸長申立のやり方(同915条第1項但書)を加味して、いかに相続放棄の判断をするべきかを理解する必要があります。
さらに現代では、核家族化が進み、被相続人(例えば親)と同居していない相続人(例えば子)が以前と比べて増加したことから、相続開始したものの、被相続人(親)の財産状況がわからないという事案が多くなってきている印象です。
相続財産調査をどれだけ尽くすかどうかも含め、注意が必要です。
相続放棄をお考えの方へ ペット信託とは?|飼い主の死後のペットを守るために